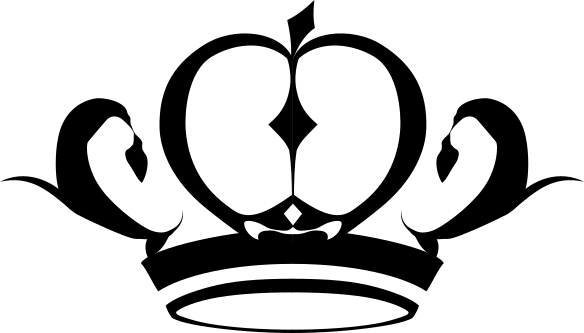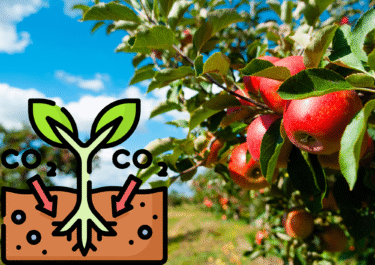桃といえば夏の代表的な果物であり、その中でもひときわ人気の高い品種の一つが「川中島白鳳(かわなかじまはくほう)」です。
長野県の名産として知られ、その大きさ、美しい外観、濃厚な甘さから、まさに“桃の王様”と称される存在です。

■ 川中島白鳳の誕生と歴史
川中島白鳳は、山梨県で誕生した人気品種「白鳳」系統の桃を母系とし、長野県で選抜・固定された品種です。
1977年(昭和52年)頃から市場に流通し始め、特に長野県の川中島地域で栽培されたことからこの名が付きました。
「白鳳」系の品種は、果汁が多く、果肉がやわらかくて食味が優れていることから高く評価されており、その中でも「川中島白鳳」は晩成種として登場し、夏の終わりから初秋にかけて出荷されるため、他品種と収穫時期がずれていることが差別化の要因にもなっています。
■ 特徴①:見た目の美しさ
「川中島白鳳」はとても大玉で、1玉あたり300g前後にもなります。
果皮は鮮やかな赤桃色に染まり、日光をよく浴びた部分は真紅に近い色合いになることもあります。
果面には適度な産毛があり、店頭に並ぶとその艶やかさと色づきの美しさで一際目を引きます。
■ 特徴②:味わいと食感
川中島白鳳の最大の魅力は、その「甘さ」と「果肉の緻密さ」にあります。
糖度は13〜15度と高く、糖酸バランスに優れており、濃厚な甘みの中にわずかな酸味がアクセントとして残ります。
果肉は白肉種でありながらやや硬めで、しっかりとした歯応えがあるのが特徴です。
完熟すればとてもジューシーになりますが、やわらかすぎず、果肉がしっかりしているため、輸送にも強く贈答用にも適しています。
■ 栽培地域と気候条件
川中島白鳳は主に長野県、特に川中島平(現在の長野市周辺)で多く栽培されています。
盆地特有の昼夜の寒暖差が大きい気候と、水はけの良い土壌が、桃の糖度を高め、果実の色づきを良くする重要な条件となっています。
近年では山梨県や福島県、岡山県など他の桃の産地でも少量ながら栽培されており、地域によって微妙に風味が異なるのも魅力の一つです。
■ 食べ頃と保存のコツ
川中島白鳳の収穫時期は、例年8月中旬〜9月上旬です。
市場に出回るのはその数日前からで、冷蔵保存よりも常温で追熟させるのが基本です。
表面を軽く押してみて、少し弾力を感じるくらいが食べ頃。
食べる数時間前に冷蔵庫で冷やすと、果汁が引き締まり、より美味しく味わうことができます。
冷やしすぎると風味が損なわれるため注意が必要です。
■ おすすめの食べ方
そのまま生食するのが最もおすすめです。
皮を剥いて、くし切りにした果実は、まさに“天然のスイーツ”です。
また、ヨーグルトやアイスクリームに添えたり、コンポートやタルト、ジュースやスムージーにしても相性抜群です。
果肉がしっかりしているため、加工用にも適しており、ドライフルーツや缶詰などに加工されることもあります。
■ 市場での評価と人気
川中島白鳳は、その見た目の美しさと味わいの高さから、贈答品としての評価が非常に高い品種です。
特に、お盆の時期を過ぎてからも出荷が続く点で、他の早生品種とは一線を画しており、夏の終わりを告げる“最後の高級桃”として重宝されています。
百貨店や高級果物店では、贈答用として1玉500円〜1,000円程度、特選品はそれ以上の価格で取引されることも珍しくありません。
■ 栽培の難しさと農家の工夫
川中島白鳳は、病気にやや弱い面があるため、防除や剪定、摘果作業など栽培には手間がかかります。
また、収穫のタイミングが数日でも遅れると果実が割れたり、糖度が落ちるなどのリスクも高いため、熟練した農家による細やかな管理が必要です。
また、樹勢が強いため、樹の成長をコントロールしながら果実をつけさせる技術も求められます。
これらの理由から、量産よりも品質重視で栽培されることが多いのです。
■ 川中島白鳳の今後
近年は品種改良や新しい桃の開発も進んでいますが、川中島白鳳の持つ味の良さや存在感は今なお根強い人気があります。
特に「固めで甘い桃」が好まれる現代の嗜好にも合っており、今後も安定した需要が見込まれる品種です。
観光農園でのもぎとり体験などでも人気があり、長野県を訪れる人にとっては“旅の味覚”として記憶に残る存在でもあります。
■ まとめ
川中島白鳳は、大玉で美しい外観、濃厚な甘み、ほどよい硬さを兼ね備えた高品質な晩成種の桃です。
長野県の自然環境が育てた逸品であり、見た目・味・贈答性のすべてに優れているため、桃好きにはぜひ一度味わってほしい品種といえるでしょう。
晩夏にしか出会えないその貴重さも、川中島白鳳が「桃の王様」と呼ばれる理由の一つです。