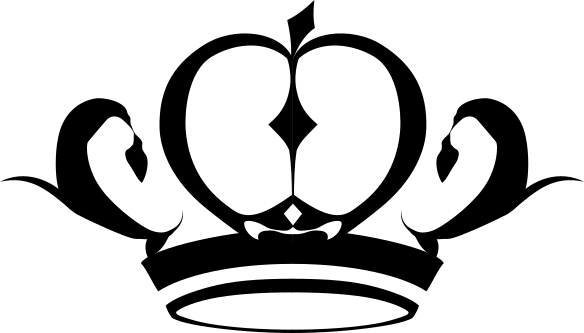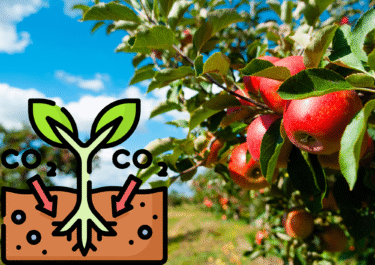目次
最初に:腐植酸と堆肥は別物?
- 結論から言えば、「腐植酸」と「堆肥」は違うものですが、深く関係した存在です。
- 両者の役割や成分は重なっている部分もあり、「土を豊かにする」という目的は共通しています。

腐植酸とは?
- 定義:植物や動物の遺体が長期間、土壌中の微生物により分解・再合成されてできた高分子有機酸。
- 性質:
- 黒褐色で水に溶けにくい(フルボ酸は水溶性)
- 土壌に長く残って保肥性や微生物環境を改善する
- 自然界では:泥炭、レオナーダイト(亜炭)などに多く含まれる
堆肥とは?
- 定義:落ち葉、草、動物ふん尿、食品残渣などを微生物の力で分解・発酵・熟成させた有機性肥料。
- 性質:
- 多くは茶色〜黒色のふかふかした有機物
- 肥料(栄養)というより、土壌の物理性と生物性の改善材
- 手作り可能:家庭でも腐葉土や生ごみコンポストとして製造可能

腐植酸と堆肥の違い一覧表
| 比較項目 | 腐植酸 | 堆肥 |
|---|---|---|
| 成分の正体 | 腐植物質(有機酸) | 分解途中〜完熟した有機物の混合体 |
| 主な機能 | 保肥力、キレート効果、微生物活性 | 通気性改善、水持ち向上、微生物の住処 |
| 肥料成分 | 含まない(ほぼ炭素) | 窒素・リン酸・カリなどを含むことが多い |
| 分解の状態 | 非常に分解が進んだ安定成分 | 分解中の有機物も多く含む |
| 使用目的 | 土壌の化学性改善、肥料効率UP | 土壌の物理性・生物性改善、土づくりの基盤 |
| 作りやすさ | やや手間がかかる(糖分・発酵管理が必要) | 比較的簡単に作れる(落ち葉・生ごみなどで可) |
| 成分の安定性 | 非常に安定(何年も土に残る) | 発酵段階によって異なる |
| 使用タイミング | 生育期に希釈して潅水または葉面散布 | 元肥・定植前に施用 |
| 植物への直接効果 | 間接的(栄養の吸収を助ける) | 少量ながら直接栄養を供給することもある |
腐植酸は堆肥から生まれる?
- はい、その通りです。**腐植酸は「堆肥の熟成が進んだ成分の一部」**です。
- 堆肥をよく発酵・分解させると、中に腐植酸やフルボ酸が含まれてきます。
- つまり、「堆肥を丁寧につくる → 土に入れる → 腐植酸が土中で増えていく」
という自然の流れが存在します。
それぞれの使い方・おすすめシーン
腐植酸が向いている場面
- 土壌の保肥力を上げたいとき(肥料が効きにくい土)
- 微量要素の吸収を良くしたいとき(鉄欠乏など)
- 化学肥料を使うが、効率を上げたいとき
- 病気に弱い作物の根圏環境を改善したいとき
- 液肥や葉面散布として使いたいとき
使用例:液体腐植酸を500倍に希釈して葉面散布(月1〜2回)
堆肥が向いている場面
- 土が固い、排水が悪いなど物理性に問題があるとき
- 微生物の働きが弱い、作物の根が張らないとき
- 連作障害を避けたいとき
- 農薬や化学肥料に頼らない土づくりをしたいとき
- 畝立て前・耕うん前など土壌改良にじっくり時間が取れるとき
使用例:1㎡あたり2〜3kgをすき込み、2〜3週間おいて定植
組み合わせると最強!
- 実は、腐植酸と堆肥はセットで使うと相乗効果があります。
- 堆肥 → 有機物・微生物の住処を供給
- 腐植酸 → 微生物の活性化と養分吸収の補助
- 例:畑の元肥に「完熟堆肥+腐植酸液を潅水」
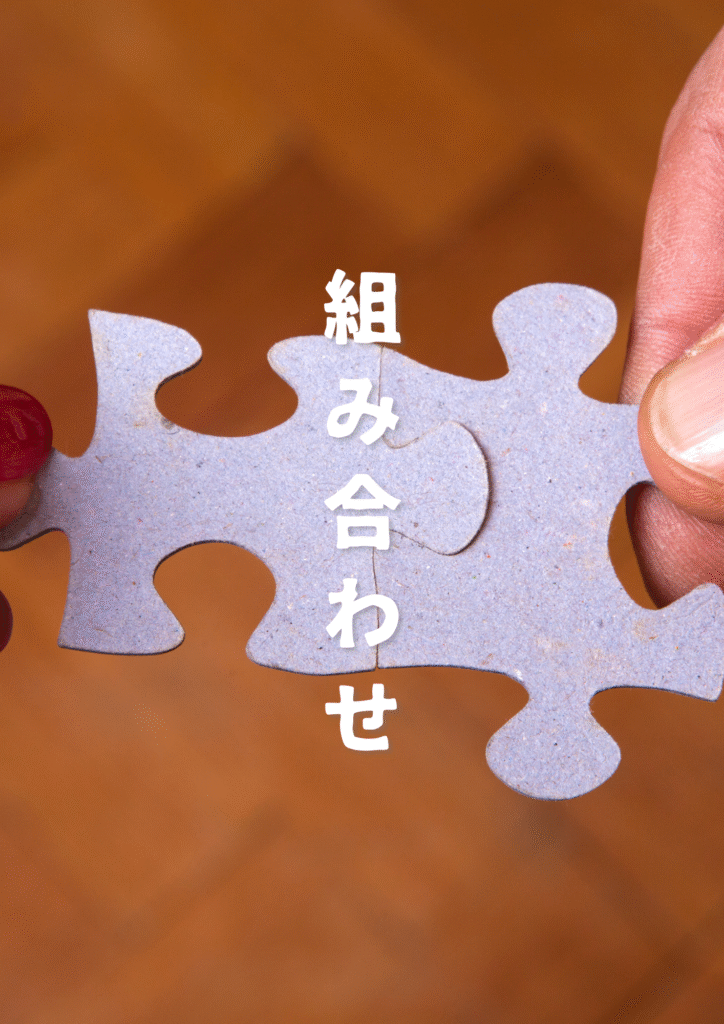
間違いやすいポイント
- 腐植酸は「肥料」ではない
肥料成分はほとんどなく、効果は間接的 - 堆肥も「肥料」ではない
栄養補給ではなく「土づくり」が主目的 - 腐植酸はすぐに効くわけではない
継続的に使って「じわじわ効く」タイプ
まとめ
- 腐植酸は「土壌の化学性・微生物環境を整える」スペシャリスト
- 堆肥は「土の構造をふかふかにする」土台づくりの要
- どちらも目的が違うので、使い分け・併用がベスト
応用編:腐植酸入り堆肥を作るには?
- 落ち葉・もみ殻・家畜ふんを使って堆肥を作る
- 発酵段階で、黒砂糖+微生物資材+水を加えて発酵促進
- 十分に発酵し、色が黒く、香りが甘酸っぱくなればOK
- この堆肥には自然な形で腐植酸が豊富に含まれる
「自作腐植酸堆肥」はコストもかからず、環境にもやさしい!
こんな人におすすめ
無農薬・有機農業をしたい人
土の調子が悪くて作物が育たない人
化学肥料の使用量を減らしたい人
土を長期的に育てたい人