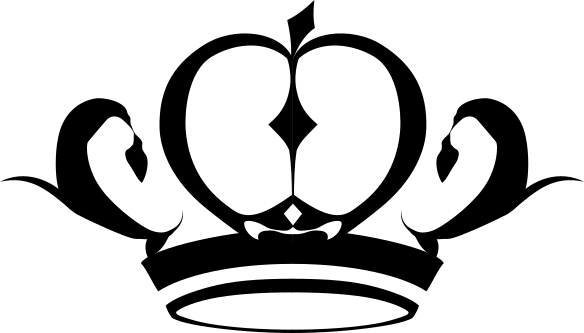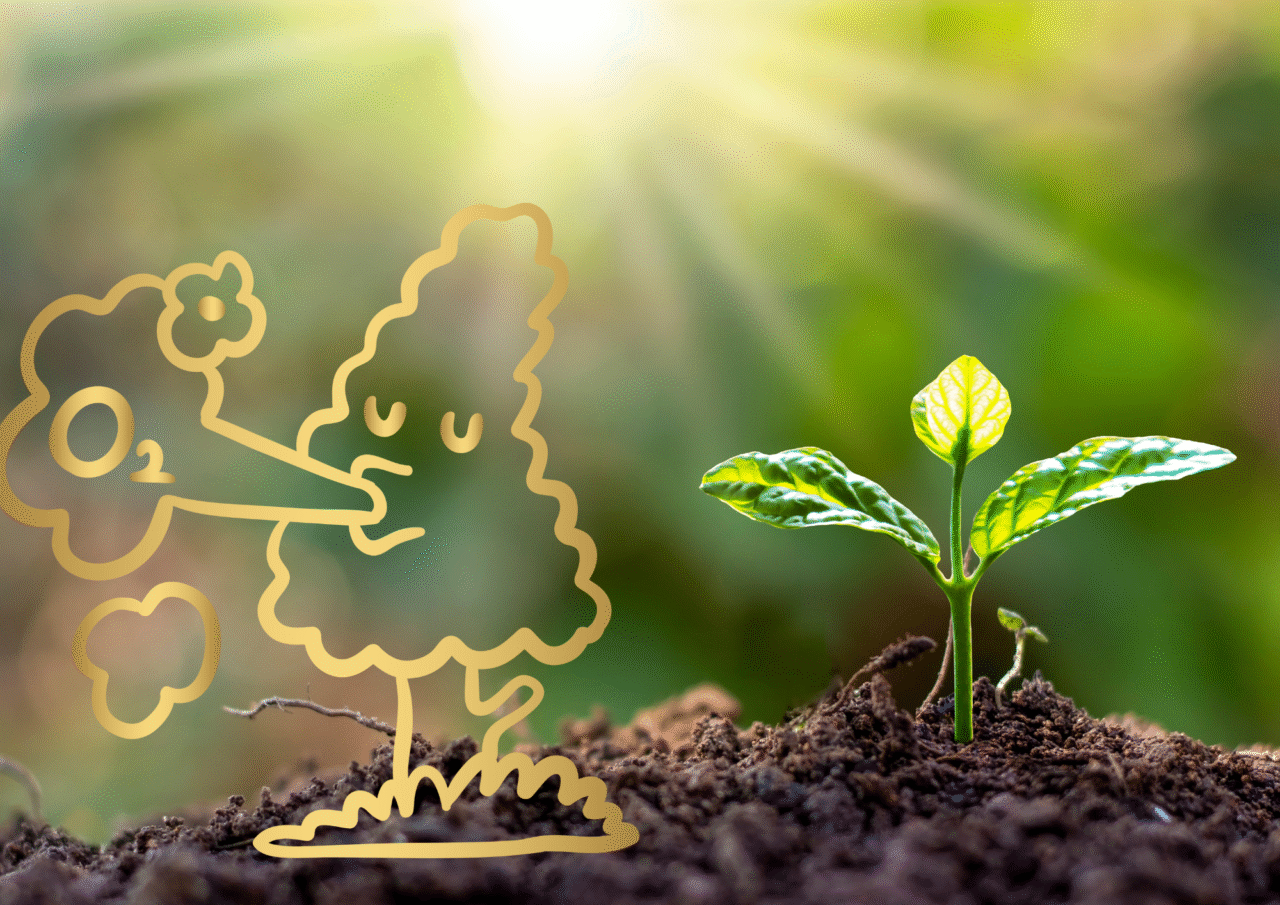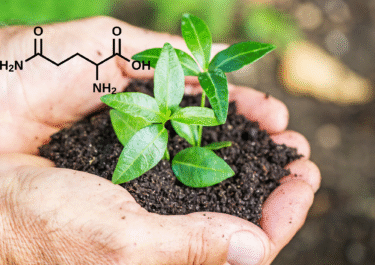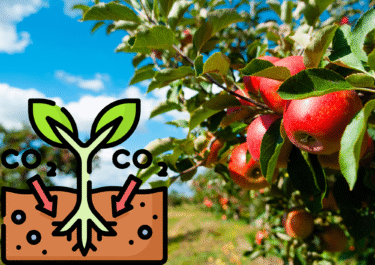果樹栽培において「土づくり」は成功の7割を占めるといわれている。そして、その土づくりの中でも「物理性」は約5割を占めるとも考えられており、根の環境づくりにおいて最も基本であり、最も影響力のある要素である。物理性を無視した土壌では、いかに肥料や農薬を適切に投入しても、植物は本来の力を発揮できない。
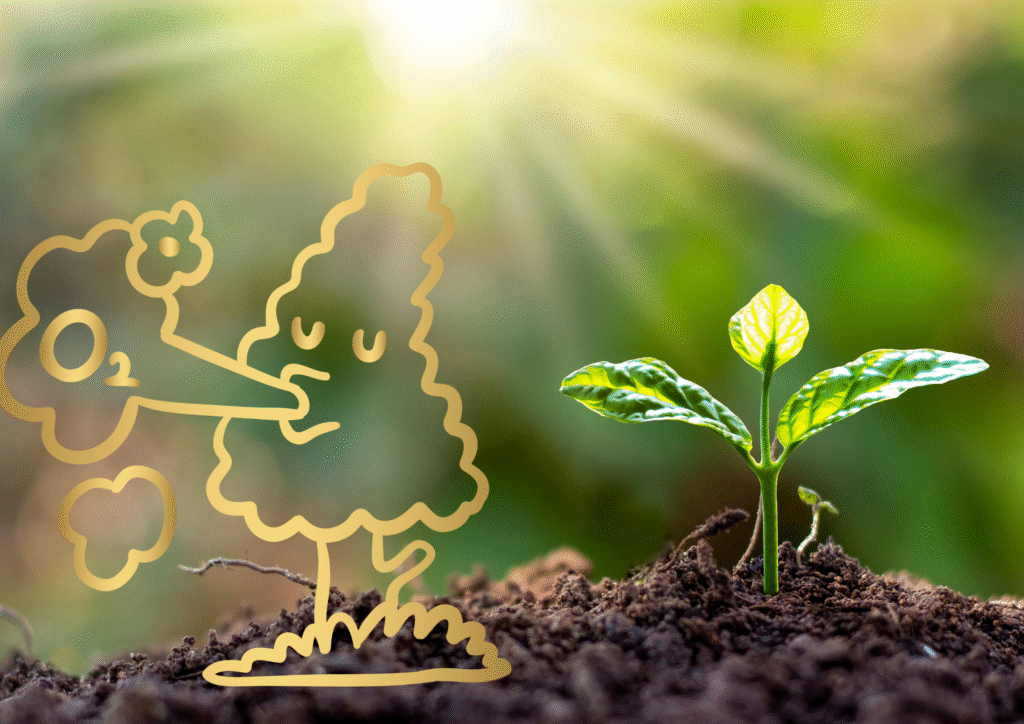
以下に、土壌の物理性とは何か、なぜ重要なのか、どうやって改善・管理すべきかを詳しく解説する。
土壌物理性とは何か?
土壌物理性とは、土の「物理的な構造」や「性質」に関する要素であり、具体的には以下のような項目が含まれる。
- 排水性(過剰水分を排出できる力)
- 通気性(根が呼吸できるだけの空気の保持)
- 保水性(水分を適度に保つ力)
- 透水性(水が浸透していく速さ)
- 団粒構造の形成度合い
- 土壌硬度・緻密さ(耕盤層の有無など)
これらの物理性が適正でないと、根が十分に張ることができず、水や肥料の吸収が阻害され、病害虫のリスクも高まる。
果樹栽培における物理性の重要性
果樹は多年生作物であり、一度植えると10年〜数十年同じ圃場で栽培を継続する。そのため、作物の根が長期にわたって良好な環境で育つことが前提条件となる。特に果樹の根は地中深く広がる性質があり、根が自由に伸びることができるかどうかが、以下のような点に直結する。
- 樹勢(木全体の元気さ)
- 花芽形成(翌年の果実の準備)
- 果実の肥大と糖度の向上
- 耐病性・耐暑性の確保
- 根腐れや病害(フザリウム、疫病など)のリスク回避
したがって、物理性を無視した果樹栽培は、まさに「砂上の楼閣」であり、長期的に安定した収量と品質を求めるには、まずこの物理性を整えることが必要不可欠である。
土壌物理性の問題点とその影響
以下に、物理性が悪い場合に生じる典型的な問題とその影響を示す。
- 排水不良(過湿)
→ 根腐れ、酸欠、病害多発(特に梅雨期や長雨でリスク増) - 土壌の過乾燥
→ 根の活性低下、果実の肥大不良、日焼けリスク増 - 通気性不足
→ 根の代謝低下、有害ガス(メタン・硫化水素)発生 - 硬盤層の存在
→ 根の伸長阻害、乾湿のムラ、栄養吸収の偏り - 表層土壌の締まり
→ 表面流出、水の染み込み不良、雑草の優先発芽
こうした問題があると、たとえ十分な施肥を行っても、それが根に届かなかったり、吸収されなかったりする。これを「潜在的欠乏」といい、見た目には肥料が足りているのに、生育が悪いという状況を招く。
良好な物理性の条件
果樹栽培に適した土壌物理性の条件としては、以下のような特徴が望ましい。
- 表層から60cm以上にわたって、均一な団粒構造を持っている
- 適度な隙間があり、水はけと水持ちのバランスが良い
- 耕盤や硬い層がなく、根が自由に深くまで伸びられる
- 大雨の後でも水が数時間以内に引き、ぬかるみが残らない
- 表面が硬くなりにくく、雑草や作物の芽が容易に出る
これらを満たす土壌では、果樹の根が活発に活動し、土壌微生物との共生もスムーズに進むため、肥料効率が高くなり、病気にも強くなる。
物理性の改善方法
土壌の物理性は、時間をかけて改善する必要がある。以下に、一般的な物理性改善の手法を挙げる。
- 有機物(堆肥、バーク、もみ殻、稲わら)の継続的な施用
→ 土壌団粒化を促進し、通気・排水性を向上 - 耕盤破砕(プラソイラやサブソイラの活用)
→ 硬盤層を破壊し、深層への水と空気の移動を可能にする - 高畝栽培の導入
→ 排水性が悪い土地では、畝高30〜50cmの高畝を作ることで過湿を防ぐ - 暗渠排水の設置
→ 特に粘土質土壌や水田転用地では、根本的な排水対策として効果が高い - 草生栽培や緑肥の導入
→ 根が張ることで自然耕うん効果を得られ、地表硬化も防げる
一時的な改良だけではなく、毎年継続的に有機物を投入し、地力の蓄積を図ることが重要である。
圃場の物理性を診断する方法
土壌物理性は目で見ても判断しにくいため、簡易的に以下の方法で診断できる。
- 水たまりの持続時間を確認(排水性の目安)
- スコップで掘って根の伸び方を見る(根が横に広がっていないか)
- 手で握ってほぐれやすいか確認(団粒の有無)
- 土壌硬度計による貫入抵抗測定(硬盤層の有無)
- 雨後のぬかるみや表面硬化の有無(通気・浸透性の目安)
また、地形的に低地や傾斜地の下側に位置している圃場では、もともと排水性が悪い傾向があるため、改良の必要性が高い。
改良の優先順位と順序
- 耕盤の有無を確認し、必要に応じて破砕
- 暗渠・明渠の整備により根本的な排水対策を実施
- 高畝をつくって水はけを確保
- 有機物の投入を継続し、団粒構造の維持を図る
- 草生・緑肥栽培により微生物活性と土壌改良効果を促進
物理性の改善は、初期に大きな改良を行い、その後は毎年の有機物管理で維持していくという「基礎構築+維持管理型」の考え方が重要である。
結論:物理性を制する者が果樹を制す
果樹栽培において、土壌の物理性は根の健康、土壌微生物の活性、肥料の効率、病害のリスク、収量や品質に至るまで、すべての基盤を支える要素である。
どれだけ高価な肥料を施しても、根が張れない土壌では吸収されず、効果が現れない。逆に、しっかりとした物理性を確保できていれば、限られた肥料でも健全な栽培が可能となる。
つまり、「物理性を制する者が、果樹を制す」と言っても過言ではない。果樹園の永続的な健全経営のために、まずは圃場の物理性を見直し、整えるところから始めることを強く推奨する。