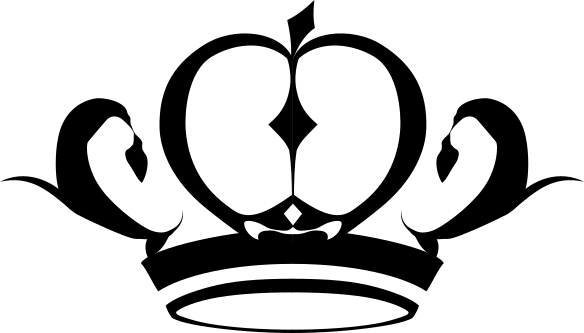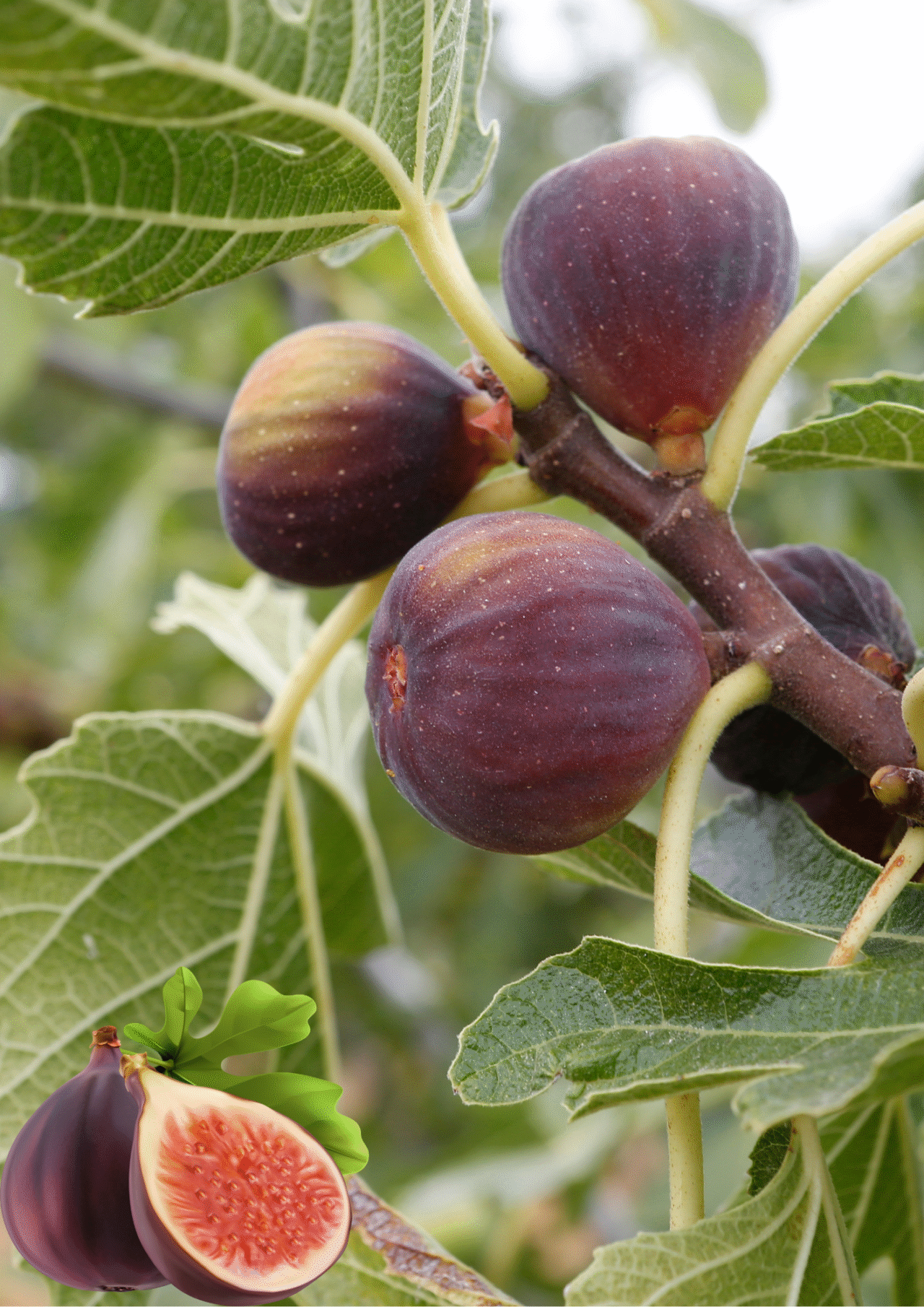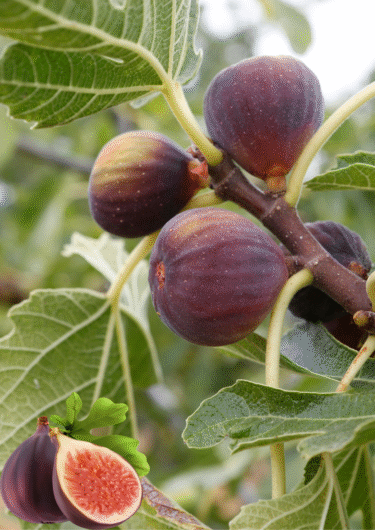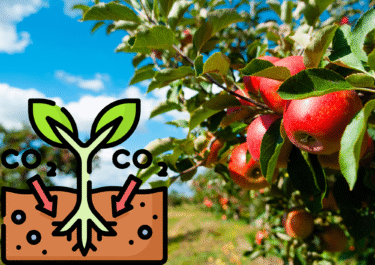~家庭菜園からプロ栽培、そして加工利用まで~
- 1 1. イチジクとは?-その魅力と歴史
- 2 2. イチジクの品種と選び方
- 3 3. イチジクの栽培基本スケジュール
- 4 4. イチジク栽培の手順とコツ
- 5 土づくり・定植
- 6 5. 病害虫とその対策
- 7 6. 鉢植え栽培も可能!
- 8 7. 収穫と熟期の見極め方
- 9 8. イチジクの加工・保存法
- 10 9. 栽培のメリット・デメリット
- 11 10. 長野など寒冷地でも育てられる?
- 12 まとめ
- 13 【1月〜2月】冬(休眠期)
- 14 【3月〜4月】春(芽出し期・植え替え適期)
- 15 【5月〜6月】初夏(生育旺盛期)
- 16 【7月〜9月】夏(収穫期)
- 17 【10月〜11月】秋(最終収穫・休眠準備)
- 18 【12月】初冬(完全休眠期)
1. イチジクとは?-その魅力と歴史
イチジク(無花果、英: Fig)は、クワ科イチジク属の落葉小高木で、果実のように見える可食部は「花嚢(かのう)」と呼ばれる器官。
原産地は中東〜地中海沿岸で、古代エジプト・ローマ時代から栽培されてきた最古の果物のひとつです。
栄養価の高さや薬効が古くから評価されており、食物繊維、カリウム、カルシウムが豊富。消化酵素「フィシン」も含み、整腸や肉料理の軟化にも使われてきました。
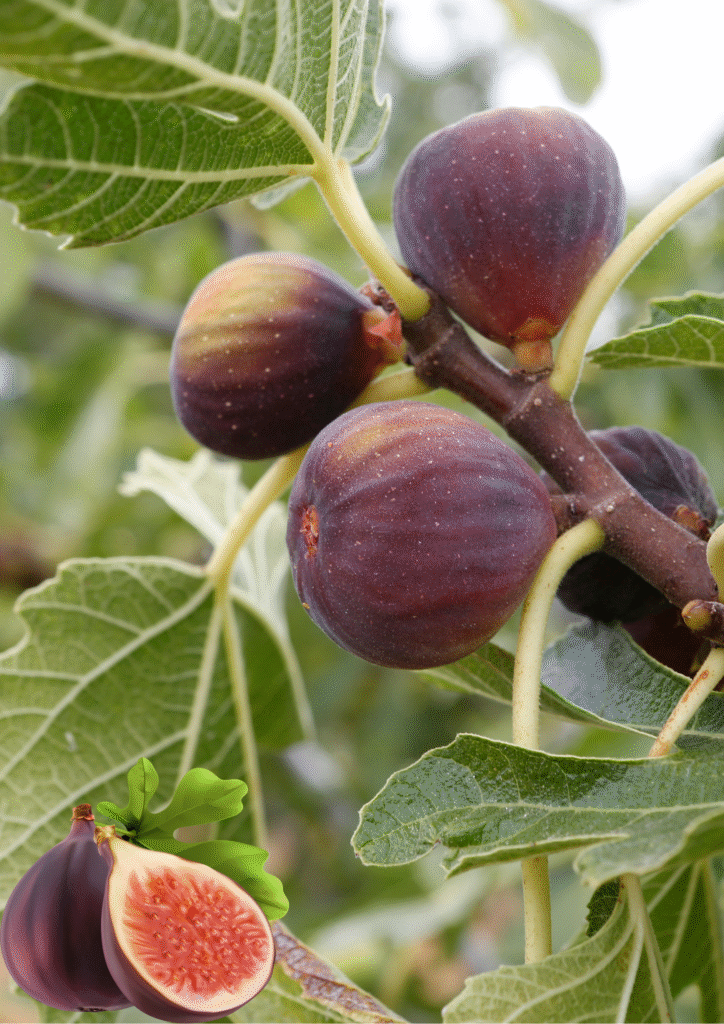
2. イチジクの品種と選び方
日本ではおもに以下の3系統が栽培されています:
【1】在来系(ホワイト系)
- 《蓬莱柿(ほうらいし)》:最も普及している在来種
- 甘みはほどほどで水分多め。生食・加工両方OK
- 果実はやや小ぶり、熟すと皮が割れる
メリット:栽培が易しく、収量も多い
デメリット:完熟果の流通が難しい
【2】ドーフィン系(レッド系)
- 《ドーフィン》《ネグローネ》《バナーネ》など
- 果皮は紫〜赤、果肉は赤褐色。濃厚な甘み
- 完熟時はジャムのような濃密な食感
メリット:糖度が高く、見た目も美しい
デメリット:高温多湿にやや弱い。裂果しやすい
【3】ホワイト系改良品種
- 《ブリジャソット・グリース》《カドタ》《ロンドボーデックス》など
- 果皮が黄白〜緑色、果肉は赤〜ピンク
- さっぱりとした味で、洋菓子向けに人気
メリット:果皮が薄く加工に最適
デメリット:雨に弱く裂果しやすいものもある
3. イチジクの栽培基本スケジュール
| 月 | 作業内容 |
|---|---|
| 12〜2月 | 落葉期の剪定(整枝・更新剪定) |
| 3〜4月 | 定植・植え替え・堆肥入れ |
| 5〜6月 | 芽かき、支柱立て、追肥 |
| 7〜9月 | 収穫ピーク、病害虫管理、水管理 |
| 10〜11月 | 最終収穫、葉落ち後の掃除 |
4. イチジク栽培の手順とコツ
土づくり・定植
- 水はけの良い砂壌土〜壌土を好む
- pH6.0〜6.5程度
- 元肥:堆肥3〜4kg/株、完熟鶏糞など
日当たり
- 日照が極めて重要(1日6時間以上)
- 日陰では果実が熟しにくくなる
水やり
- 若木はやや多め。夏場は朝夕の水やりが重要
- 過湿は裂果の原因になるため排水対策を
剪定
- 果実はその年に伸びた枝の先端に実る
- 冬の剪定は、前年の主枝を残し、前年の実がなった枝を間引く
- 夏剪定で混み合った枝を間引くことで風通し改善

5. 病害虫とその対策
カミキリムシ類(幼虫が幹を食害)
- 幹に穴が開き、フンが出る
- 幼虫を針金で突いて駆除、薬剤注入も可
イチジクコバチ(裂果原因)
- 裂果部分から侵入。袋かけで予防
すす病、うどんこ病
- 風通しが悪い・肥料過多で発生しやすい
- 剪定と適正な施肥が重要
6. 鉢植え栽培も可能!
- 樹勢が強すぎない品種を選ぶ(ドーフィン系など)
- 10号鉢以上、深さ30cm以上を推奨
- 2年に1度は植え替え・剪定が必要
7. 収穫と熟期の見極め方
- 果実が下を向いてくる
- 果皮にしわ・ひびが出る
- 指で軽く押すと柔らかい
- 完熟の一歩手前で収穫することで裂果や虫害を防げる
※完熟果は非常に日持ちが悪く、冷蔵しても1〜2日で劣化します。
8. イチジクの加工・保存法
ドライいちじく
- スライスして天日干し or 60℃前後の乾燥機で8〜10時間
- ヨーグルトやパン生地に活用
ワイン煮・シロップ漬け
- 赤ワイン・砂糖・レモン・スパイスで煮詰めて瓶詰め
- 高級デザートや前菜にも活用可能
コンフィチュール(果実ジャム)
- レモン汁を加えることで色鮮やかに
- 砂糖は果実の30〜50%で調整
9. 栽培のメリット・デメリット
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 放任でも実がつきやすい | 熟果の日持ちが短い |
| 整腸・美容効果など栄養価が高い | カミキリムシなど害虫リスクあり |
| 1株でも収穫でき、家庭菜園向き | 夏場の裂果が多発する年も |
| 生食・加工どちらでも美味 | 夏剪定などの管理が若干手間 |
10. 長野など寒冷地でも育てられる?
イチジクは耐寒性が比較的低く、霜が降りる地域では防寒対策が必要です。
長野県のような寒冷地では、以下の対策が有効です:
- 冬期は株元をワラや不織布で覆い、寒風から守る
- 根元を切り詰め、春に再発芽させる「切り戻し剪定」
- 鉢植えで冬は屋内かハウスに移動
寒冷地向けには「ドーフィン」や「ネグローネ」のように、短期間で収穫できる品種が向いています。
まとめ
イチジクは初心者でも挑戦しやすく、かつ収穫後の活用幅が非常に広い果樹です。
栽培の手間も少なく、工夫次第で「自家製ドライフルーツ」や「無添加ジャム」など、健康志向にもマッチした食材として活躍します。
品種選びと剪定・水管理のコツをつかめば、毎年たっぷりと収穫が楽しめる果樹です。
あなたの庭や鉢植えで、“いちじくのある暮らし”を始めてみませんか?
【1月〜2月】冬(休眠期)
- 落葉が終わったら**剪定(整枝・更新剪定)**を実施
- 枯れ枝、込み合った枝、前年に実をつけた枝を切除
- 寒風・霜対策(株元をわら・寒冷紗で覆う)
- 鉢植えは霜の当たらない場所へ移動
【3月〜4月】春(芽出し期・植え替え適期)
- 定植・鉢植え替えの最適期(根の更新もこの時期に)
- 元肥を施す(堆肥3kg+化成肥料など)
- 新芽が出たら芽かき(1箇所1芽)
- 支柱を立て、風対策を行う
【5月〜6月】初夏(生育旺盛期)
- 主枝・副枝の誘引・仕立てをする
- 草丈が伸びすぎないよう先端を摘心
- 追肥(化成肥料または液肥を月1回程度)
- 雨が続く時期は裂果防止に袋かけも有効
- 病害虫(特にカミキリムシ)に注意して点検
【7月〜9月】夏(収穫期)
- 収穫期:熟したらすぐに収穫(下向き+やわらかさが目安)
- 収穫後の枝は切らず、次年の花芽が育つまで残す
- 水管理:乾燥しすぎないよう注意、特に鉢植えは朝夕水やり
- 裂果・虫害対策として適度な日よけ・雨よけも有効
【10月〜11月】秋(最終収穫・休眠準備)
- 遅れて熟す実を収穫
- 葉が黄変したら病害がないか確認して落葉を回収
- 来年の剪定準備:枝の状態を観察してメモ
- 鉢植えは徐々に水やりを減らす
【12月】初冬(完全休眠期)
- 樹が完全に休眠に入る時期
- 鉢植えは霜の当たらない場所に移動
- 越冬準備完了(寒冷地では根元にワラ、全体に寒冷紗)