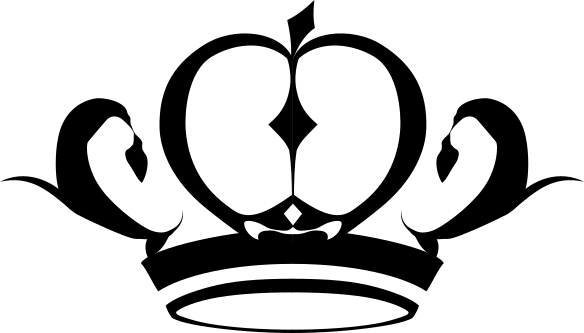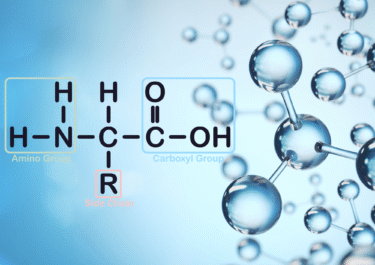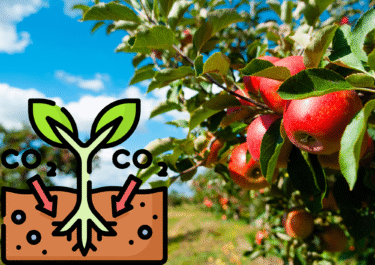このうち近年、特に注目されているのが「土壌の生物性」です。リンゴは多年生作物であり、同じ場所に10年、20年と根を張り続けるため、根圏における微生物の健全なバランスが、果樹の寿命・収量・果実品質を大きく左右します。

1. 土壌の「生物性」とは?
土壌の生物性とは、土の中に存在する微生物や小動物、菌類などの生物活動の状態や多様性を指します。目に見えないけれども、根の成長・病害の抑制・養分の分解供給に関わる“縁の下の力持ち”です。
主な構成要素は以下の通り:
細菌類(バクテリア)
放線菌(ストレプトマイセス属など)
真菌類(糸状菌、キノコ類など)
酵母
原生動物・線虫・ミミズなど
根圏微生物群(リゾバクテリア、菌根菌)
2. なぜリンゴ栽培にとって生物性が重要なのか?
リンゴの根は繊細で浅く広がる性質があり、土壌の状態に強く影響されます。特に以下の点で、生物性は重要です。
根のまわりの微生物が栄養分を供給
病原菌の発生を抑制
有機物を分解して栄養に変える
土壌構造を改善して通気性・保水性を向上
根と共生することで根の成長を促進
長期的に健康な根圏環境を維持するためには、「良い微生物」を活かす土壌設計が欠かせません。
3. リンゴに関わる主な土壌微生物とその働き
◆ 有用な微生物
菌根菌(アーバスキュラー菌根菌)
→ リン酸や微量要素の吸収を助ける。リンゴとの共生例も多い。
リゾバクテリア(根圏細菌)
→ 根の成長促進物質(オーキシンなど)を分泌。病害菌を抑える効果も。
放線菌
→ 有機物分解に優れ、病害菌の抑制にも寄与。
セルロース分解菌
→ 腐植化を促進し、CECや保水性の向上に貢献。
窒素固定菌(フリーリビング型)
→ 空気中の窒素を土中に供給(果樹に直接供給するわけではないが、地力向上に貢献)。
◆ 有害な微生物
フザリウム菌
→ 根腐れや萎凋病の原因菌。
リゾクトニア菌
→ 若木に立ち枯れ症状を起こす。
ナミハダニ、センチュウ類
→ 根を食害し、微細な傷から病原菌が侵入。
連作障害の原因菌
→ 同じ作物を連続して栽培すると、特定の有害菌が土壌中に蓄積。
4. 生物性の高い土壌の特徴
有機物に富み、腐植含量が高い
団粒構造が形成されている(ふかふかの構造)
根のまわりに白い菌糸やコロニーが見られる
雑草の生育が旺盛で多様
土の匂いが“森林の腐葉土”に近い
5. 生物性が低い(悪化した)土壌の兆候
表層が硬く、下層はぬかるみやすい
雑草が少なく、特定種のみが異常繁殖(スズメノカタビラなど)
根が黒ずんでいる、根腐れが多発
水はけが悪く、酸欠状態になりやすい
病気が出やすく、薬剤の効果が持続しない
6. リンゴ園の生物性改善・維持方法
有機物の積極的な投入
完熟堆肥(牛ふん、落ち葉堆肥など)を年1回以上施用
粗大有機物(樹皮、籾殻、剪定枝チップ)のすき込み
草生栽培で緑肥(クリムソンクローバー、ライグラスなど)を導入
土壌還元消毒の活用(必要時)
太陽熱と有機物で、土壌病原菌を抑える
連作障害対策にも有効(夏季に実施)
菌資材・微生物資材の使用
有用微生物(EM菌、光合成細菌、トリコデルマ菌など)の資材散布
土壌環境を整えてから使用することが重要(酸素不足や塩害があると効果低下)
通気性・透水性の確保
深耕・サブソイラーで下層の硬盤を破砕
マルチング(樹皮・藁)で表土の乾燥防止と微生物活性維持
農薬使用の抑制
不必要な殺菌剤・殺線虫剤の連用は微生物の多様性を損なう
必要な場合も局所散布・最低限にとどめる
7. リンゴの樹齢とともに進む「微生物環境の劣化」
リンゴ園では年を追うごとに:
圃場が踏み固められ物理性が低下
有用微生物の多様性が減少
病害菌の蓄積による土壌病の発生率増加
といった悪循環に陥りやすくなります。
これを防ぐには:
毎年の有機物施用
下草の管理(除草剤多用を避ける)
土壌診断と、微生物分析の導入
若木の定植前に土壌改善を徹底する
8. 実践事例(長野県・青森県のリンゴ園)
青森県の有機リンゴ農家
→ 木材チップと米ぬかを混ぜた堆肥を3年連続施用
→ 地力の回復、病害の減少、果実の糖度向上が確認された
長野県の草生栽培園地
→ 白クローバーを全園に導入、マメ科の根粒菌による窒素供給とミミズの増加を確認
→ 土壌団粒構造が改善、貯水性向上による干ばつ耐性が向上
9. 微生物と化学性・物理性の関係
微生物はpHが適正なとき最も活性化する
有機物がなければ微生物も生きられない
土壌が締まりすぎていると酸欠 → 好気性微生物が減少
土壌塩分(EC)が高いと、有用菌が死滅しやすい
つまり、生物性は物理性・化学性に支えられてはじめて発揮される要素でもある。
10. 今後の課題と展望
気候変動により「土壌乾燥・豪雨」など極端な気象が増加
土壌環境が不安定化 → 微生物バランスも崩れやすい
対策として、炭素資材(バイオ炭・木炭)や新型微生物資材への期待が高まっている
また、大学や研究機関による**「土壌DNA解析」**なども進み、今後は“可視化された生物性”に基づく施肥・土壌改善も実用化が進むと考えられる。
まとめ:微生物を味方につける土づくりが、リンゴを変える
リンゴ栽培は、単に肥料を与えて果実を育てるのではなく、「根と微生物の共生環境」を整えることが最重要です。
有機物の継続的な投入
土壌診断と微生物の可視化
圃場全体の呼吸性・多様性の維持
草生栽培など「自然の力を活かす」農法の導入
これらの実践により、病気に強く、品質の良い果実が長期にわたって安定生産できる圃場づくりが実現します。