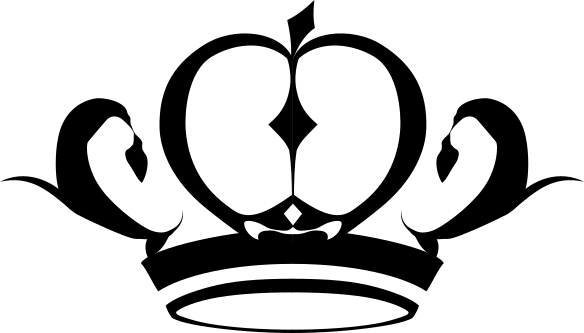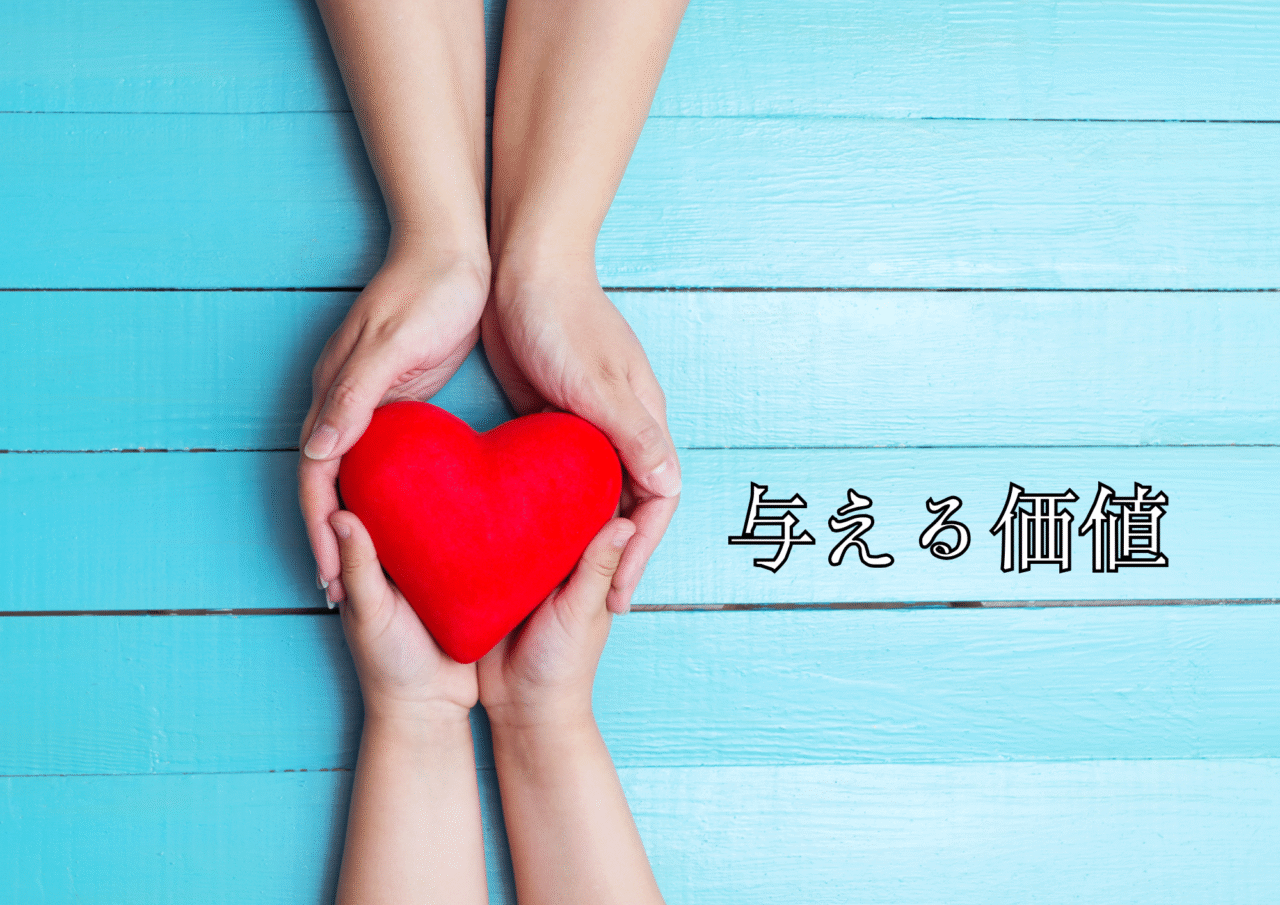長野県立科町の山あいに、小さな果樹園「アップルアート」がある。
春には白い花が咲き乱れ、夏には緑が生い茂り、秋には赤く実ったリンゴが枝先で陽を浴びて揺れている。
この場所で育ったリンゴは、ただの食べ物ではない。
それは、ある人にとっては感謝の気持ちを伝える手紙であり、ある人にとっては再会の約束の証であり、またある人にとっては、離れて暮らす家族への愛のかたちになるからだ。
私たちアップルアートは、そんな“想いをかたちにする果実”をつくっている。
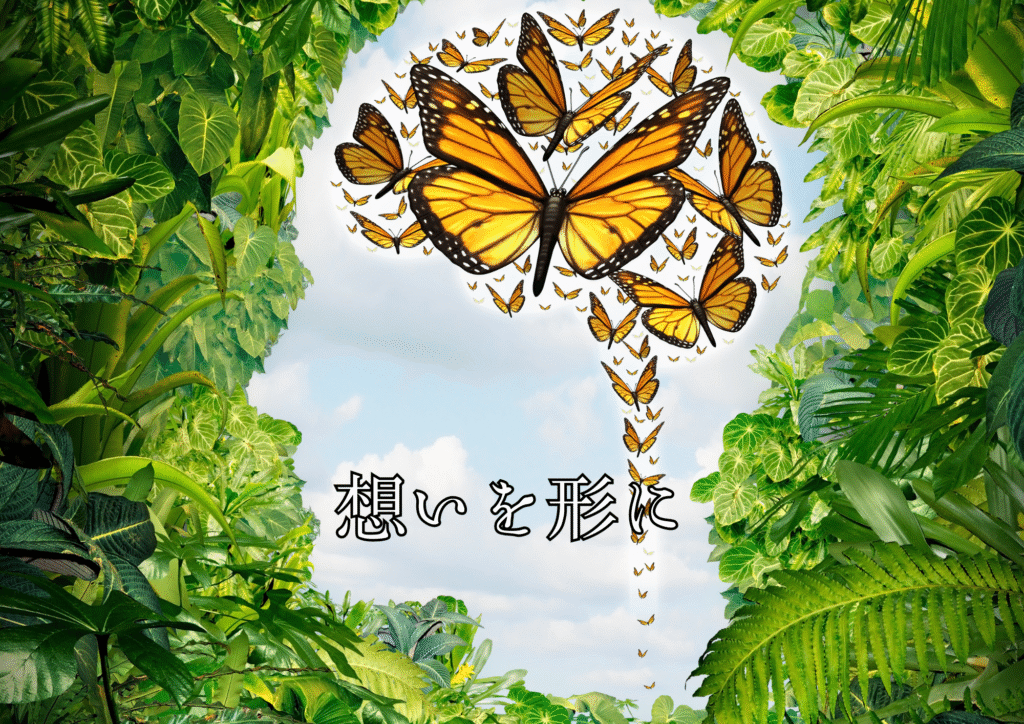
もちろん、生計を立てるために果物を売っているのは事実だ。
けれども、それ以上に大切にしていることがある。
それは、果実に“意味”を込めて届けること。
たとえば、あるお客様は「病気で入院している父に、元気づけたい」と言って、リンゴを注文してくださった。
一口食べると「信州を思い出すよ」と、父は目を細めて微笑んだという。
また、こんなこともあった。
毎年結婚記念日に「今年も一緒にいられて幸せです」と果物を贈り合う夫婦がいる。
私たちはその思い出の一部に、ほんの少しだけ関われていることを誇りに思っている。
果実を収穫し、選び、磨き、刻む。
その一つひとつの作業に、機械では代替できない手仕事がある。
リンゴの表面に浮かび上がる文字や絵柄は、単なる加工ではなく、贈る人の「想い」を宿すキャンバスだ。
自然が描く色、農家が育てた味、そして私たちが添える心——
そのすべてが融合して、世界にひとつだけの「果実のアート」になる。
この仕事をしていると、時々、自分たちがリンゴを売っているのか、感情を届けているのか、わからなくなることがある。
だがそれこそが、私たちが目指すところだ。
果実という目に見える商品を通して、見えない価値——喜びや感動、つながりや想い——を届けること。
その“与える価値”こそが、私たちアップルアートの存在理由なのだ。
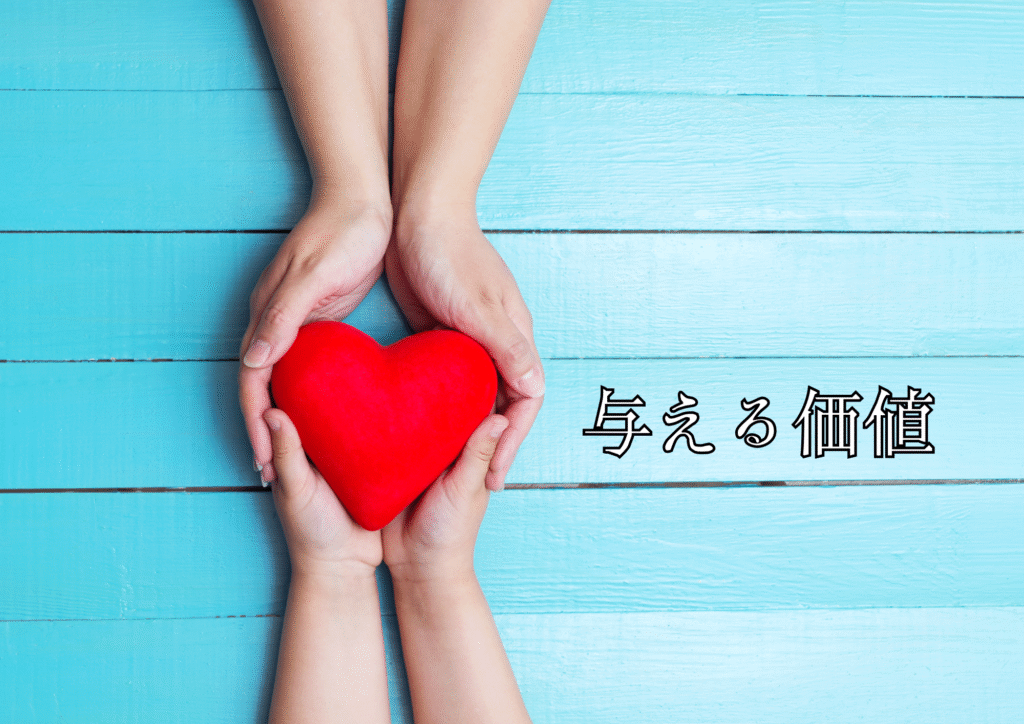
得ることは、もちろん必要だ。
私たちがこの仕事を続けていくには、収穫し、売上を得て、農園や職人たちの生活を支えていかねばならない。
だが、それだけでは「事業」は成り立っても、「人生」は築けない。
お客様に感動してもらい、「ありがとう」と言ってもらえる。
果実がつなぐ絆の中に、自分たちの仕事の意味を見いだす——
そんな体験の積み重ねが、私たち自身の人生を豊かにしていくのだ。
あるとき、あるお客様から一通の手紙が届いた。
「亡くなったおばあちゃんに、毎年アップルアートのリンゴを贈っていました。
最後の年も、ちゃんと届きました。ありがとうございました。」
その手紙を読んだとき、私たちは言葉を失った。
リンゴが、ただの食べ物ではなかったということを、あらためて実感した。
果実には、人生を彩る力がある。
それを知っているからこそ、私たちは今日もまた、一本一本の木に向き合い、一つひとつの果実に向き合う。
アップルアート——
それは単なる果物ブランドではない。
それは「与えることに意味がある」という生き方を体現するチームであり、
果実を通して人と人をつなぐ“アーティスト”たちの集まりなのだ。
得るもので生計を立て、与えるもので信頼と人生を築く。
それが、私たちアップルアートの誇り。